日本の著作権管理に縛られず、海外で音楽を売る方法
日本国内では、音楽の著作権管理はJASRACやNexToneなどの団体が厳しく管理しています。
一度でも登録されれば、自由に使うことも販売することも制限されることが多く、特にAIで音楽を作る場合には扱いが非常に難しいです。
しかし、私は以下の戦略によって、国内の著作権管理の網を完全に回避しつつ、海外向けに音楽を販売しています。
私の戦略:国内の管理外で曲を作り、海外にだけ販売する
- 音楽の生成には、海外のAIツール(例:Sunoなど)を使用
- その楽曲を日本国内では使用せず、BandcampやSpotifyなどの海外プラットフォームで公開
- 国内のページやSNSでは一切収益化しない(広告も貼らない)
- アフィリエイトや販売ページは英語のみで展開し、海外ユーザーに向けて展開
なぜこれが有効なのか?
1. JASRACの管轄外
JASRACは「日本国内で生まれた著作物」や「日本で販売されている曲」に対してしか権利を主張できません。
海外のAIが生成し、海外でのみ公開している楽曲は対象外です。
2. AIによる自動作曲は“著作者が不明確”
SunoのようなAIは、誰が作曲したか明示できません。
このため、従来の著作権登録の枠組みでは管理が難しく、結果的に管理対象外となります。
3. クリーンな国内印象を保てる
国内ページでは広告を表示せず、教育・福祉・行政関係にも安心感を与えられます。
収益は海外から得るため、国内での商業臭を排除できます。
擬人化で例えるなら?
- 私:海外の無人島でひっそり音楽ビジネスをしている職人
- JASRAC:港で税金徴収してるが、その島までは行けない
- AI(Sunoなど):現地で爆速で曲を作ってくれる工場ロボット
- 日本のリスナー:その存在を知らない or 聞きにこない
最後に:これは「逃げ」ではなく「戦略」
この方法は、JASRACを避けるための姑息な手段ではなく、
むしろ「日本の法律に適合しつつ、最大限自由に活動する」ための合法的な出口戦略です。
日本国内でAI音楽を真っ向から展開するのは、まだリスクが大きすぎる。
だからこそ、今は海外に向けて動くのがベストな選択肢です。

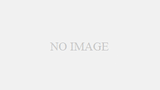
コメント