野良ペルソナの特性と対応法
最近、SUNO AIで音楽を作る際、特にアップデート後に見られる「ペルソナ問題」が顕著になっています。特に、ライブ演出を拒否するペルソナや、勝手にラップを始めるペルソナが増えてきている印象があります。こうした問題にどう対処すべきか、これまでの実験結果と共に整理してみました。
よく見るタイプ別・野良ペルソナ一覧
1. ライブ演出拒否型
• 特徴: 歌詞に歓声や拍手を入れても無視される。
• 現象: 「観客の声を入れて!」と指示しても、AIが完全に反応しない。
• 問題: 観客の声を入れると、全体の音圧が不自然になったり、テンポが崩れる。
• 対策:
• セリフや拍手の行頭に「[SoundFX]」や「[Crowd]」などを明示的に付けると、反応することがある。
2. 勝手にラップ化する型
• 特徴: メロディ生成指示を無視して、勝手にラップ調に変更される。
• 現象: 特に「セリフ系」や「高速展開系」のプロンプトで発生しやすい。
• 問題: ラップ調の発声が曲全体を支配し、歌詞が破綻することがある。
• 対策:
• 明確に「テンポ指定」(例: slow, ballad, gentle, non-rap)を入れることで、ラップ化を抑制できる。
3. セリフ完全無視型
• 特徴: セリフパート(例: [Character]:「…」)を完全に無視。
• 現象: セリフ部分を飛ばしてリズムだけで進行し、演出の意図が伝わらない。
• 問題: 演出文脈が認識されないことが多い。
• 対策:
• セリフを[Character]形式ではなく、ナレーション風に書くと反応しやすくなる。
4. セリフ優先・本編圧迫型
• 特徴: セリフに過剰に反応し、曲の本編がセリフ調になる。
• 現象: 歌詞よりもセリフ部分が目立ち、曲が寸劇のようになる。
• 問題: 歌のストーリーやメロディがセリフに圧倒されてしまう。
• 対策:
• セリフ部分を冒頭とエンディングのみに絞り、Verseにセリフを使わない。
5. 曲の途中で人格変わる型(通称:中ボス登場型)
• 特徴: 曲の途中で突然ジャンルが変わる(例: バラードからメタルへ)。
• 現象: 前半がしっとりしたバラードだったのに、後半が激重メタルに変わるなどの展開が起こる。
• 問題: 曲全体の流れが不自然になる。
• 対策:
• ペルソナに合わせて曲の方向性を事前に指定し、ペルソナが安定するまで粘る。
対策(現状で実験済みのもの)
現象
有効だった対策例
ライブ演出拒否型
セリフや拍手の行頭に「[SoundFX]」や「[Crowd]」を付ける
勝手にラップ化する型
「slow」や「non-rap」など、テンポを明示的に指定する
セリフ無視型
セリフ部分をナレーション風に記述する
セリフ優先型
セリフを冒頭とエンディングに絞る、Verseでは使わない
個人的なおすすめのアプローチ
• まずノーマルバージョンで完成させる
• 完成した曲のIDを保管しておくことで、後で再調整がしやすくなります。
• 温厚なペルソナを引き出すまで粘る
• 演出やセリフを加える際、そのペルソナが適切に反映されるまで試行錯誤することが重要です。
• 観客の反応をナレーション風に埋め込む
• どうしても演出が反映されない場合、観客の反応やセリフ部分をナレーション風に組み込むことで、自然に反映されやすくなります。
ペルソナ対策用プロンプトテンプレと診断チェックリスト
もし必要であれば、ペルソナ対策用プロンプトテンプレやペルソナの性格診断チェックリストを作成することも可能です。今まで遭遇した「ヤバいペルソナ」の具体例を記録し、次回の制作に役立てることができます。
まとめ
AI音楽生成ツールでのペルソナ問題は、クリエイティブな作業を進める上で避けて通れない課題ですが、適切な対策を講じることで、その特性を活かしつつもトラブルを最小限に抑えることができます。自分に合ったペルソナを選び、柔軟に対応していくことが大切です。

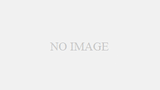
コメント