AIはペット、だから飼い主の責任
配信者の姿勢が問われている
近年、AI音楽の配信が急増する中で、いくつかのディストリビューターがAI楽曲を締め出す動きを見せています。「AIだから」という表面的な理由が語られがちですが、実際にはもっと根本的な原因があります。
それは、AIを使っている「人間側の姿勢」が問題視されているということです。
メタデータは「しつけ」の鏡
メタデータの不備、クレジットの不統一、ふざけたジャンル名…。
こうした小さな問題の積み重ねが、配信プラットフォームにとっては大きな負担となります。人間の手で一つひとつ審査される中で、悪目立ちすれば当然「AI=迷惑な存在」と誤解される流れも生まれます。
AIはペット。振る舞いは飼い主次第
AIに罪はありません。
命令された通りに作曲し、入力された通りの情報で配信されるだけです。
つまり、AIはあくまで「ペット」であり、その振る舞いは飼い主(=配信者)に全責任があるのです。
・どんな環境で育てるか
・何を食べさせるか(プロンプトやタグ)
・誰に会わせるか(どのリスナー層に届けるか)
すべて、私たちの選択で決まります。
「人としてどうか」が問われる時代
私が小さい頃、親からこう教わりました。
「自分がされて嫌なことを、他人にするな」
AI時代になっても、この教えは変わりません。
・雑なデータ提出で、配信側の作業が増える
・規約を読まずに、勝手な配信を繰り返す
・クレームを入れるだけで感謝しない
そんな人が増えれば、業界全体の「民度」が下がり、結果的に真面目なAIユーザーまで排除される空気が作られてしまいます。
締め出されるのは「AI」ではなく「中身」
誠実にAIと向き合い、丁寧に作品を届けている人まで巻き込まれてしまう。
この現実を変えられるのは、「真面目に取り組んでいる側の声」と「行動」だけです。
私自身も、最初は失敗だらけでした。
しかし、途中で「これは飼い主の責任だ」と気づき、反省し、丁寧に対応を始めました。
最後に:AIと共に生き残るには
音楽業界の中でAIが生き残るには、「ルールを守れる使い手」が必要です。
技術の進化ではなく、「人間の姿勢」が未来を決める。
AI音楽が市民権を得るために、今できることを、ひとつずつ積み重ねていきましょう。
[end]

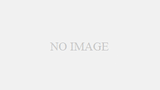
コメント