下手な歌声を“評価不能化”する心理音響戦術
はじめに
音楽を聴くとき、人は自然と「上手い」「下手」という評価軸で聴いてしまいます。だがこの価値基準は、本当に絶対的なものでしょうか?
本稿では、あえて「下手な歌声をバレないようにする」ことを目的に構成された異常な音源設計手法を紹介します。これは単なるふざけた遊びではなく、情報戦・芸術戦略としての音響心理操作です。名付けて「音幻自在(おんげんじざい)」。
背景と課題意識
- 歌の上手下手は「比較」によって生じる
- 聴覚・脳は予想外の連続に弱く、混乱しやすい
- 評価軸そのものを揺るがせば、下手は“存在しない”ことにできる
音幻自在の技術構成
以下の技術要素を組み合わせて「判断不能化」を実現します。
- ジャンルの高速切替:フォーク→メタル→演歌→ユーロビート→合唱などを1曲内で次々切り替える。
- ボーカルの人格分離:性別・声質・感情・年齢が異なるペルソナを小節ごとに交代。
- 左右音像の入れ替え:右耳と左耳で違う人の声が交互に移動する。
- 本人歌唱の「混入」:誰が歌ってるか分からなくなるタイミングで下手な本人歌唱を挿入。
- リズム破壊と手拍子:異様な手拍子+AIボイスの組み合わせで注意を撹乱。
実践例(概要)
- A曲とB曲を用意し、それぞれ別のジャンル・構成に変化。
- 「良い子のみんなも手拍子だ!」などのセリフで不意打ち。
- 途中で関係ないB曲へ強制遷移してからA曲へ戻る。
- 本人の歌声もエフェクトで曖昧化し、他と混ぜてしまう。
効果と考察
実際に試聴したリスナーは以下のような状態に陥ります:
- 「誰が歌っているのか分からない」
- 「ジャンル変化が激しすぎて評価できない」
- 「頭が疲れる」
- 「なんかすごいけど、何が起きてるのか分からない」
このように、聴覚と判断力にバグを起こさせることで「歌が下手かどうか」を思考する余裕すら奪ってしまうのです。
応用可能性
- VTuberやカオス系クリエイターの演出戦略
- 子ども番組的なカオス構成(悪用厳禁)
- ライブパフォーマンスにおける「観客混乱」演出
結論
音幻自在は、歌唱力という既存の価値基準を破壊し、「そもそも比較できない状態」を作り出す戦術です。孫子の兵法でいう「戦わずして勝つ」に近い。
今後、AI音楽時代の中で「下手な人の戦い方」として、あるいは逆に「評価を超えた混沌の表現」として注目されるかもしれません。
なぜ「音幻自在」が必要だったのか
実は、「忍者歌唱法」を試そうとしたことがある。
AIボーカルと自分の声を組み合わせて、あえて“下手さ”を忍ばせるという発想だ。
しかし――現実は厳しかった。
録音環境は、解約済みのiPhone 5と現役のiPhone SE2。
iPhone 5にヘッドホンを接続して歌入りの曲を聴きながら、SE2を逆さにしてマイク代わりに使った。
文字通り、「たった二台のスマホだけ」で録音したわけだ。
だが、録った音を再生してみると、自分でも最後まで聴いていられないほど下手だった。
それでも、何とか公開しようと粘った。編集でどうにかならないかと考えた。
でも、どう頑張っても「下手」は隠せなかった。
だから「音幻自在」が必要だった
この体験が、「音幻自在」という発想につながった。
“下手な歌声をどうにかする”のではなく、
“聞き手の認知をバグらせることで、評価そのものを成立させなくする”という逆転のアプローチ。
上手くなれないなら、土俵そのものを破壊すればいい。
次回は、この「音幻自在」という概念をどう構築し、どう実行するかを具体的に紹介していく。
おわりに
本記事はヤズカクオにおける実験報告の一部です。もし興味を持った方がいれば、自分自身でもこの“音幻自在”の構成を試してみてください。

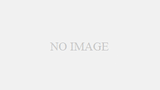
コメント